お探しのキーワードで記事検索できます
MENU
キーワードをタップ
プロフィール
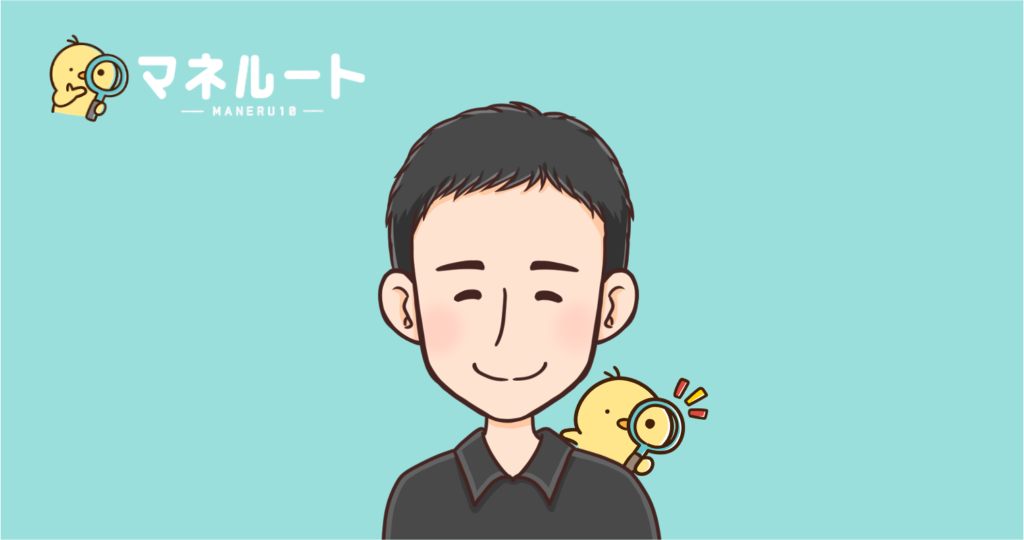
マネル
どうも、マネルート運営者のマネルです。
当ブログでは、8年間で2,000人以上コンサルしてきた現役FPの僕(マネル)が、お金にまつわる「知らないだけで損してる」をなくすため、初心者でもマネして実践できるお金のノウハウを発信しています。
ご質問やお仕事のご依頼は、お問い合わせフォームまで。

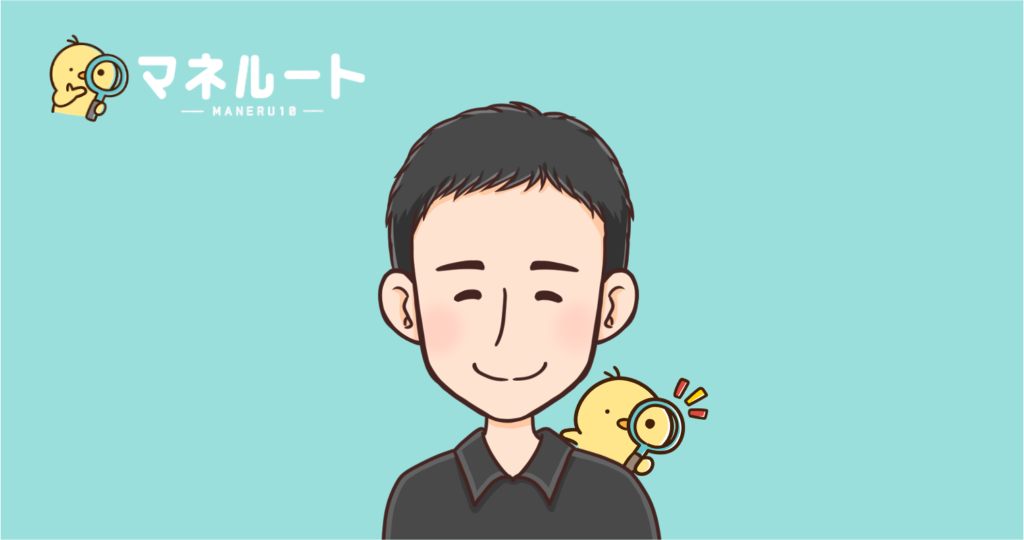
マネル
どうも、マネルート運営者のマネルです。
当ブログでは、8年間で2,000人以上コンサルしてきた現役FPの僕(マネル)が、お金にまつわる「知らないだけで損してる」をなくすため、初心者でもマネして実践できるお金のノウハウを発信しています。
ご質問やお仕事のご依頼は、お問い合わせフォームまで。


医療費控除とは、一定の基準を超えた医療費を支払った場合、所得税や住民税の控除が受けられる制度のことです。
医療費控除は確定申告時に内容や金額を記入する必要があるため、仕組みや控除の条件などについてきちんと理解しておくことが重要です。
本記事では、所得控除の仕組みや対象となる費用などについて、詳しく解説していきます。
医療費控除とは、確定申告の際に所得税や住民税の控除が受けられる制度です。以下では、医療費控除の仕組みや要件について解説します。
医療費控除は所得控除のひとつで、支払った医療費に応じて税金を計算し直す仕組みです。
会社員の場合は所得税の還付が受けられ、個人事業主の場合は確定申告に反映して節税することができます。
<医療費控除の金額>
医療費控除の金額は、以下の式で計算されます。
「実際に支払った医療費の合計額」ー(保険金等で補填される金額)ー10万円
*総所得金額が200万円未満の場合は、総所得金額の5%の金額
なお、医療費控除の上限金額は200万円と定められています。
出典:国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」
<医療費控除の対象期間>
医療費控除の対象期間は、その年の1月1日から12月31日までとなります。
医療費控除の要件は、以下の2つがあります。
(1)納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2)その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。)。
出典:国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」
毎年2月中旬頃になると、健康保険組合から「医療費のお知らせ」という通知が届きます。そこに医療費控除の対象となる金額が記載されているので、参考にするとよいでしょう。
医療費控除には、対象となる支払いとそうでない支払いがあり、注意が必要です。対象となる費用には、主に以下のようなものがあります。
医療費控除の対象となる費用
医療費控除の対象になる費用には、診療・治療・療養にかかった費用が含まれます。以下のような費用は、すべて医療費控除の対象です。
医療費控除の対象になる診療・治療・療養費用
上記のように、医療機関にて支払った費用は基本的に医療費控除の対象になると考えて良いでしょう。
歯の治療に関しては、基本的に自由診療も含め医療費控除にできますが、以下のような対象とはならない特殊な条件もあります。
歯の治療にかかった費用で医療費控除の対象とならないもの
上記以外の場合は、通院費やローンで支払った料金等を含め、医療費控除の対象となります。
出典:国税庁「No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療の具体例」
出産にかかる費用も医療費控除の対象となり、主なものは以下のとおりです。
医療費控除の対象となる出産にかかる費用
また、入院の際に用意した寝巻きや洗面具等の身の回り品の購入費用は、医療費控除の対象にはならないため注意しましょう。
出典:国税庁「No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例」
医療費控除の対象になる交通費は、医師の診療等を受けるために必要と認められる交通費に限られます。
ただし、これは公共交通機関を利用した場合によるもので、自家用車を利用した際に発生するガソリン代や駐車代は対象とはなりません。
通院などの交通費に関する一般的な取り扱いは、以下のとおりです。
医療費控除の対象となる交通費
公共交通機関の運賃は、領収書がない場合がほとんどです。領収書がない場合は、「いつ、だれが、どの医療機関に行ったか」などをメモなどにまとめておき、医療費控除を申請する際にすぐに思い出せるようにしておきましょう。
また、タクシーの利用を余儀なくされる場合において、そのタクシー代の中に高速道路の利用料金が含まれているときは、その高速道路の利用料金も医療費控除の対象になります。
セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)とは、特例の医療費控除のことです。
これは、健康の維持増進及び疾病予防への一定の取組を行う個人が、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)の購入費用について所得控除を受けることができる制度です。
2022年1月以降、制度が5年延長され、税制対象医薬品の範囲が拡充されました。
セルフメディケーション税制の適用条件は、以下のとおりです。
セルフメディケーション税制の利用条件
出典:厚生労働省「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について」
ただし、通常の医療費控除を適用した場合は、セルフメディケーション税制は受けられないのでご注意ください。
なお、セルフメディケーション税制対象品目は、厚生労働省ホームページ「セルフメディケーション税制対象品目一覧」で確認でき、一部の対象製品は以下のマークで識別できます。

医療器具・医薬品の購入にかかった費用は、医療費控除の対象となります。主な例は、以下のとおりです。
医療費控除の対象となる医療器具・医薬品にかかった費用
このような医療に関する備品等の購入については、基本的に医療費控除の対象になると考えてよいでしょう。また、おむつ代も医療費控除の対象となりますが、細かい要件に注意しなければいけません。
傷病によりおよそ6ヶ月以上寝たきりの状態で療養しており、おむつを使用する必要があると認められる場合のおむつ代(この場合、医師の発行する「おむつ使用証明書」が必要)は、医療費控除の対象になります。
また、おむつ代についての医療費控除を受ける2年目以降において、介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付する「おむつ使用の確認書」を「おむつ使用証明書」に代えることができます。
出典:国税庁「医療費控除の対象となる医療費」
医療に関わる費用で医療費控除の対象になるものは多いですが、医療費控除の対象にはならない費用もあります。具体的に対象外となる医療費は、以下のとおりです。
医療費控除の対象とならない医療費(医療行為)
医療費控除を受けるためには、個人事業主はもちろんサラリーマン・アルバイト・パートで働く人であっても、確定申告を行わなければいけません。
具体的な医療費控除の申請方法について詳しく知りたい方は、別記事「医療費控除の申請方法とは?確定申告時の必要書類や計算のやり方を分かりやすく解説」をあわせてご確認ください。
医療費控除は、正しく申告することで節税や所得税還付につながります。ただし、対象となる費用や仕組み・要件を理解しておかなければいけません。
また、医療費控除とセルフメディケーション税制の併用はできないため、確定申告の際はどちらがより控除額が大きくなるかを計算してから申告を進めましょう。
この記事で紹介したような仕組みや対象となる医療費を正しく理解して、医療費控除を活用してみてください。

この記事が気に入ったらフォローしよう
コメント